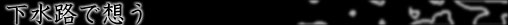
沙苗の腕に半ば怖々と触れて、俺は「なあ」と言う。沙苗は「なに?」と振り向く。なにと問われて返す言葉はないから抱き寄せようとするのだが、彼女は身を捩り、そして半ば力ずくで体を引いた。
そして俺の顔も見ずに「お金貸してる男とは、しない」と言った。溢れ出そうだった俺の"気持ち"は、萎えてさっと引いただけでなく、逆流する下水のように不快な臭いと共に裡に吹き上がった。俺に返す言葉は何もなく、取るべき正しい態度はひとつも思い付かない。沙苗にしては上出来の台詞じゃないかと、自虐的に思う。まるで女の家に転がり込んだ無職の小僧に戻った気分だ。
寝室を出てダイニングに入った。昔観たフランス映画の、下水路の地下分岐点を思い浮かべてみた。いや、そんなもんじゃないよなぁ。そもそもフランス映画の下水路と、分譲住宅のダイニングルームには大きな隔たりがありはしないか? ともあれ、ダイニングルームというのは、うんざりした気分に浸るのに丁度良い場所だ。少なくとも下水路よりは良い。なぜなら酒がある。
そんなことをぐだぐだ考えながら呑んでいたら、いつの間にか前の小径を人が走る時間になっていた。空瓶はあいつの頭にでもぶつけてやれば良いか? ふざけた模様のタイルが敷き詰められた舗装路に血まみれになって倒れ込む女性ジョガーを想像してエロチックな衝動を覚えつつ、眠りに落ちた。
気がついたら昼。沙苗はいない。いないよなぁ、仕事だから。俺はと言えば、こうして郊外の建て売り住宅の、狭くて変な形のダイニングでお目覚めだ。予定はない。
そしてまだ心の中は下水臭い。俺にはリセットが必要だと考えている内に、麻美の事を思い出した。誰より俺を好きだと言っていた奇特な女。今思えば幻みたいだ。でも下水路の出口なんていうのは幻みたいな物じゃないか? とにかく、今の俺は麻美に逢わないとならない。
■
ビール、2杯目。待ち合わせの時間はとっくに過ぎている。
ドアの開く音がしたが、目の端に映ったのは、中年の女が一人店に入って来るところだった。俺はすぐに自分のグラスに視線を戻す。
待ち合わせは、以前よく使ったスタンドバー「OFF」にした。麻美は「あたし、こういう店あんまり好きじゃないんだよね」と一度言ったことがある。それでも俺は指定する店を変えなかった。彼女がそれに合わせるべきだと、そう考えていたからだ。俺が傲慢だったのかもしれないし、彼女が鈍重だったのかも知れない。そんな俺を、なぜ麻美は好きでい続けられたのかは分からない。本当は大して好きではなかったなら俺に合わせる意味もなかっただろう。俺はどちらでも良いと思っていた。しかし今日の待ち合わせを「OFF」にしたのは俺の鈍感さなのか。
ともあれ麻美は、以前の様に約束の時間をやや過ぎてから「OFF」に現れた。現れたのだったのだが、俺はその事に暫く気がつかなかった。
麻美はどちらかというと童顔で同い年には見られない。以前に街中で偶然知人と出会して後日に「若めの彼女だね」と言われ、心の中でそのどちらも否定しつつ微笑んで誤魔化したものだった。付き合ったのは5年間だったか。互いに重ねる齢は何かの拍子に認識したが、しかし緩やかに変わる景色に対しては互いに鈍感なもので、時の流れそれ自体を認識することはあまりなかった。久しぶりに逢う麻美のことをそんな風に思い出していたら、目の前の椅子に先ほどの中年女が腰掛けようとしていた。
「待ち合わせで、その席は空けて貰っているんですが」と言うつもりで顔を上げると、歳の分かりにくい雰囲気ではあるけれど明らかに20近くは年上であろうその女は、適量の微笑みを口の端に浮かべたまま言うのだった。
「久しぶり。元気にしていた?」
麻美だった。年齢以外は。
■
「中にしても良かったのに」
放心したかの様に、息を吐きながら麻美が言う。
それは周期のためなのか。あるいは“この麻美”はもうそういう歳だったりするのではないだろうか。そんなことを考え始めると、つい顔からは目を逸らしてしまう。体の方にそれ程“違和感”はなかったのだが、それが、実際に年齢差など関係ない物だからなのか、単に俺が彼女の体躯に慣れていたからなのかは判然とはしない。何かとても懐かしい所に居る様な感覚に襲われる。ずっとこうしていたいと思う。
しかしそれと同時に別のところに違和感を覚えた。そうだ、俺の知っている麻美は、そもそもそんなことは言いもしなかった。愛し合う前には当たり前の様に念入りなシャワーを浴び、スキンは必ず着け、そして遊びで付き合ったにしては刺激的な行為は何もなかった。おかしな話だが、何が楽しくて付き合っていたのかも思い出せない。俺のことはともかく、麻美の気持ちも意味も、俺には分からない。
「前はそんなこと、言いもしなかったよな」
そう言うと、麻美は目の下を膨らませるような微笑み方をして、「“前”っていつよ、“前”って」と言った。
そうだ。“前”っていつだよ? 俺は段々いろんな事が分からなくなって、頭がクラクラしてきていた。
気が付くとダイニングで寝ていた。家の中に人の気配はない。
麻美とは、もう何年も前に別れていたのだった。は? 沙苗と結婚する前の話か? それって何年前の話だよ。あれから携帯は何台か替え、とうに連絡は取り様もなくなっていた。
玄関脇のクローゼットに掛けっ放しだったジャケットを手に取って、胸ポケットを漁る。確か何本か残っていたよな。自分の家すら禁煙のご時世だと。ふざけんな。
消費期限なんかとっくに過ぎた古い煙草を見つけ、咥えて火を点ける。
ああ、不味いな。最低だ。不味い。焦げた紙と、油の匂いしかしない。
下水路にはお誂え向きだ。
 |